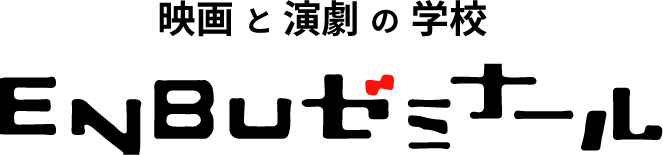TEACHER
INTERVIEW 02
講師インタビュー
中澤正行さんインタビュー
映画監督
中澤正行
Masayuki Nakazawa
PROFILE映画監督コース 撮影照明講座 担当講師
中澤正行(なかざわまさゆき) 『マルタイの女』(1997/伊丹十三監督)、『コンセント』(2002/中原俊監督)、『星に願いを』(2003/冨樫森監督)などの撮影助手を経て、撮影監督としてデビュー。『天使の卵』(2006/冨樫森監督)で、新人撮影監督に贈られる三浦賞を受賞。 ほか、撮影作品に『あの空をおぼえてる』(2008/冨樫森監督)、『午夜心跳』(10/張加貝監督)、『思春期ごっこ』(14/倉本雷大)、『ニート・ニート・ニート』(18/宮野ケイジ)、『カゾクデッサン』(20/今井文寛)など。
調べればわかるハード面より、もっと違うことを教えたい
――中澤さんは撮影監督としてご活躍の傍ら、映画監督コースで「撮影照明講座」をご担当いただいています。ENBUゼミで教鞭を取っていただくようになったのはいつ頃からですか?
もう随分昔ですが、撮影助手時代に出会った冨樫森監督が、ENBUゼミナールでワークショップ映画を作っていました。そのときにカメラマンとして何度か参加をして、それから撮影についてのワークショップを単発でやり……映画監督コースの講師をやるようになったのは、10年ほど前からですかね。
――「撮影照明講座」は例年、まずは座学から始まり、古今様々な映画の中から優れたシーンを抜粋して生徒に見せ、その内容を解説していきます。
そうですね。僕の場合は一つの手法について、具体例を一つ提示して終わりにするのではなく、なるべく多くの具体例、複数のクリップを見てもらうようにしています。その方がエッセンスを掴みやすいと思うので。
映画って、そもそもいろんな見方ができるものでしょう? そこがいいところなんですけど、教える段になるとそれが邪魔になってくるんですね。示したいもの以外の要素も見てとれてしまうので。でも、同じ手法を使っているものをたくさん並べると、何が言いたいかわかってくると思うんですね。そのためになるべく多くクリップを見せるようにしています。その方が説得力も出てくると思いますし。
――撮影の授業と言うと、技術やテクニックを習うようなイメージをもっている方も多いと思いますが、この講義では演出とも密接に関わる撮影術……いわば「映画術」のようなものを扱っていきますね。生徒からは毎年、「この講義を受けて映画の見方が変わった」という声が上がっています。このような講義は、いつから行われるようになったのですか?
撮影を教えるようになった当初から、このようなスタイルでやっています。「たくさん映画を見て、そこで何が行われているのかを考え、知識を蓄積していく」ということは、元々自分のためにずっとやってきていたことでした。正直、撮影の具体的な技術など、ハード面の知識は、検索すればいくらでも出てきますし、僕自身がそれを教えることに強い興味をもてないんです。ただ一方的に自分の知識を伝えるだけになってしまう。一方演出の面は、人に教えることで新たな発見があったりして楽しいし、なにより自分自身の勉強になります。自分がわかりきっていることを伝えるより、今興味があることを伝える方が僕のノリ方もちがうし、それを聞いている生徒にも響くと思うんです。
映画は三次元で考えるもの
――実習の授業では、生徒たちが台本を元に撮影をしていきますね。実習の時に心掛けていることはありますか?
映画それ自体は二次元のメディアですが、それだけに、なるべく立体的なものの考え方を伝えられたらいいと思っています。座学の授業にはどうしても限界があり、口では説明できても、実際いかに三次元的に人やカメラを動かすかということをわかってもらうのがなかなか難しい。ですので、そういった三次元的な動かし方、いわゆる「ブロッキング」に特化した話ができるように心掛けています。
というのもそれが、僕自身が専門学校では教えてもらえず、冒頭でもお話した冨樫監督のワークショップ映画で撮影を任せてもらったときに、初めてわかったことだったんです。撮影の初日に、僕は自分の中で事前にある程度カット割を考えていたんですね。でも現場に行ったら、冨樫さんが芝居をつけて、人物がどんどん動いていく。動き出したらもう、僕が考えてきたカット割は全然使えないわけですよ。頭が真っ白になって、その日は何とか撮ったけれど、めちゃめちゃでした。反省して次のシーンから、事前に考えていたことは全て捨てて、一生懸命その場で監督がつける動きの中でどう撮るかを考えていくようにしました。するとカメラもいい動きができて、すごく気持ちがよかった。そのときのことは忘れられないですね。現場でできたものは三次元だから、事前には考えられないんですよ。実際現場で人が動いて、それを自分が見て、カメラをどうするか考える。伝えるのはなかなか難しいですが、ワークショップみたいな形で実際動いてみるとわかるので、実習ではそういうカメラの動きも含めたブロッキングを教えたいと思ってやっています。絵コンテを描いてその通りに撮るような、平面的な映画の撮り方もあるし、それで面白い作品もたくさんありますけれど、そういうやり方はわざわざ実習をしなくても学べると思いますし、何より僕自身、三次元的なものが好きなので。
――「ブロッキング」という概念について改めて教えていただけますか?
人物を動かすこと。ステージングとも言いますが、カメラも含めて、人物をどう動かすかと言うことですね。人物が座ったままで、カメラはフィックスで……ということもありますが、それもある意味では「動かさない」というブロッキングになります。必ずしも人物を常に動かさなければならないというわけではないけれども、要は、どう配置してどう撮っていくかということですね。最近の監督はあまり動かさないでしょう。

冨樫監督がワークショップ映画でやっていたのは、まず、役者さんにお芝居をやってみてもらう。そこに全く動きはないわけです。大抵の場合台本にセリフはあっても、動きは書いていないわけですから。そうなるとカメラもあまりできることがない。でもそれじゃ面白くないから、どこかで人が立ち上がったり、振り向いたり、目線をそらしたり、という動きをつけていくわけですね。段取りで役者さんのお芝居を見ていると、座ったままでも立ったままでも、どこかでふっと目をそらす瞬間なんかがある。それを監督がめざとく見つけて、その瞬間に目をそらすだけじゃなくて、背中を向けて歩きだそうとか、動きを大きくする。そういうお芝居の生理の中でおかしくない、動機が分かる部分で動きを大きくしていく、するとカメラもそこで動かないといけないんですね。背中を見せたら、その人の顔をまた見せるのにどうするかとか。
それから、ハリウッドでは「ビジネス」と言うらしいのですが、例えば会話するシーンでも、会話以外に何かやることを与える。話しながら書類を探すとか、ペンをいじっているとか……そういった「スモールビジネス」、つまりセリフを話すこととは別に何かやらなければならないちょっとしたことを与えることによって、じゃあどこで目を上げるのか、どこでその手が止まるか、といったようなバリエーションが演出に出てくるわけです。そういうことも含めてブロッキングです。そういった演出がないと、経験のない役者さんなんかは特に、面と向かってセリフのやり取りするほかなくなってしまうわけですね。
学生さんたちの作品を観ていると、そういう演出はほとんどありません。それから、シーンの頭で人物をどう配置しているかということもその後の演出に影響が出る重要な要素ですが、そこがきちんと考えられていることも少ない。 今は昔よりたくさんの映画を観られようになって、プロもアマチュアも、二次元的な「編集の映画」はうまく撮れるようになってきていると思います。その一方で、三次元的な奥行きを活かした動きというのは、どんどん下手になってきている感じがしますね。逆に言うと、これからそこを突き詰めていくと、他人と差をつけられるかもしれません。みんな、かっこいい画を撮ることや、かっこいいカット繋ぎは上手だけれども、ブロッキングで唸るようなものってプロでもなかなかないですから。
――たしかにそういった三次元的な考え方というのは、中澤さんの講義を受けて初めて実感できたことでした。人を動かすということや空間を大きく使うこと、カメラとの距離など……。
そうですね。距離はやっぱり大切です。
例えば「クロースアップ」というのは、カメラが引いたところから望遠レンズで撮影する、被写体から距離のあるクロースアップもあるし、近づいてワイドレンズで撮るクロースアップもある。その違い、同じクロースアップの距離感の違いというのは、サイズの違いでしかない絵コンテでは出せないんですよね。
――授業を受けて、自分で撮ってみるまでは、同じだと思っていました。
絶対それは違うもので、実際に見てみないとわからないところなんですよね。逆に、見てみればレンズの知識なんかなくても誰にでもわかる。距離感という三次元的なものが、二次元の映像であっても確実に伝わるんです。やはり離れて撮ったら、離れて撮ったような画にしかならない。
それから、役者とカメラの距離をコントロールするという感覚もぜひ養ってほしいですね。どういう画が欲しいかという、絵コンテ的な画ではなくて、距離をどう撮るかという感覚があれば、登場人物の関係、即ち、ドラマを描くことができると思います。距離感というのは、単なる映像を映画に変えるファクターの一つでしょうね。
――現場でどう人を配置し動かすか、それをどう撮るか……というブロッキングの発想が身についてくると、それを考えることこそが醍醐味という気がしてきます。撮影の日が楽しみになりますね。
この楽しみを覚えたら、一生映画をやめられないと思いますよ。
見ている人は見ている
――後期の授業では、生徒たちが夏に作った短編作品を講評していただいています。毎年、一つの作品を何回も見て、きめ細やかなフィードバックをしてくださいますね。
いつもそれを楽しみにしています。すごく勉強になるんですよ。当然のことながら学生たちの作品は技術的に未熟です。それだけに、どこがどうダメなのかわかりやすいんです。この場合のどこがどうダメというのは技術的なことではなく、演出面のことを言っています。劇場公開されているような映画だと、面白くなくても、うまくいってないポイントが見えにくい。それよりもはっきりと、どこをどうすればいいというのがわかるので、それを自分の撮影にも応用できる。実はそういう罠って、初心者だけでなく、みんながはまりやすいんですよね。技術的に拙い作品だと目につきやすいというだけで、言うほど、学生が間違えることとプロが間違えることって差がないんです。
「これは真似したいな」というアイディアやエッセンスが見られることも、たまにありますよ。所詮自主映画でしかないというコンテクストで損をしている場合が多いけれど、そういうよいところにもちゃんと気づいて指摘してあげたいと思いますね。
――中澤さんにとって、いい映画とはどんなものですか?
ハッとさせられるもの、ですかね。繋がらないと思っていたものが繋がって、「あ、こういうことだったんだ」と思わされると、ぐっときます。物語的な面でも、カメラワークなどでも。
学生映画の場合だと、全体的に環境が整っていない中でそういった光るものがあって、僕がいいと思っても、ほかのお客さんでそれに気づく人は少ないのかな、とは思います。ただそういうものは必ず見てくれている人はいると思うので、そういう人が若い才能ある人たちを育てて、ちゃんとした環境の中で花開かせてくれれば、また素晴らしい日本映画の若き巨匠が誕生していくんじゃないですか。
さっきも言ったように学生たちとプロとで、間違えるところも、いいと思うところも、本当はそうじゃいけないんですけど、さほど変わらないので、あとは環境だけだと思います。「学生が撮ったもの」ということでの見せられ方と、ちゃんとした商業映画としてもうすべて用意されたものの中で見せられるのとでは、同じものであっても受け取り方は全然変わってきますから。そのためには、ちゃんとアンテナを張って引き上げてあげられる人が、見てあげて伸ばしてあげて、そういう環境で撮れるようにしてあげないといけないと思います。僕にはそこまでの力はありませんけど、誰か心ある人がね。でもやはり「見ている人は見ている」という意味では、どういうシチュエーションであろうと、「ああ、いいな」と思う人は少なからずいるはずなんです。だからできるだけたくさんの人に見てもらい、その中で気づいた人が応援してくれれば、望みはあるんじゃないでしょうか。今はさまざまな上映機会があるし、それこそ、映画祭をすっ飛ばしてYouTube公開してしまうなんてこともできるわけじゃないですか。もちろん、それで見てもらえるかどうかというのは話は別ですが、どこかで見てくれている人がいて……ということはなきにしもあらずですから。今はそうやっていろんな機会があることが羨ましいと思います。
――フィルムの時代には、たくさん撮りたくても撮れないということもありましたものね。今は撮り放題・上げ放題だから……。
そうですね。まあその分、雑になっている部分もあるかもしれませんが。
――面白い映画を作るのに、映画をたくさん見るということは大切だと思われますか?
はい。本当の天才だったら見てなくてもいいんでしょう(笑)。
でもやはり、見ていないよりは見ていた方が、見たら見ただけストックができてくると思うので。残念ながら昔の撮影所みたいに、現場にスタッフで入って学んでいくというスタイルがないに等しい。現場に入ったとして、素晴らしい監督の元につけるかどうかは、わからないじゃないですか。けれども、「作品を見る」となったときには、勝手に私淑しちゃえばいいわけですよね。小津でもヒッチコックでも。見る分には限界がなく、いいものが選べるので、やはり、たくさん見た方がいいと思います。

現場で何かが生まれる瞬間こそ楽しい
――大変映画愛の深い中澤さんですが、映画を好きになったきっかけはどのようなものでしたか?
映画をたくさん見るようになったのはちょっと遅くて、大学生になってからです。最初の頃は、格好いい俳優が出ているとか、好きなミュージシャンが言及していたとか、そういうミーハーな感覚で映画を見ていましたね。
そんな大学生活の中である日、レオス・カラックスの『汚れた血』を見て、衝撃を受けました。あの体験は大きかったですね。それから「映画をやりたい」と思うようになって、大学卒業後に日活芸術学院に入りました。学校は2年間でしたが、2年目は現場に出ていた時間がほとんどで、伊丹十三の『スーパーの女』や、Vシネマの撮影に見習いで入ったりしました。その後日活の社員になり、撮影部として数年間撮影助手をした後、フリーになりました。助手時代はいろいろなカメラマンについて、それぞれ教わることがありましたね。
――撮影監督デビューは冨樫森監督の『天使の卵』。監督からオファーされたんですか?
そうです。先ほどお話したように、助手時代に冨樫さんと、ENBUゼミやニュー・シネマ・ワークショップで、山のようにワークショップ映画を撮っていました。作品によっていろいろスタイルを変えてやったり、当時はまだ一眼がなくてビデオカメラで撮っていたのですが、深度の浅い画を撮れるようにカメラをカスタマイズしたり……あの頃は楽しかったですね(笑)。
当時作ったものの中で、今でも「あれは超えられないな」と思うショットがあります。そういうことって環境云々ではなく、その時にその場で生まれたものの中で作られるから、後からもう一度ああいうショットを……と思っても、なかなかできないんですよね。
――ぜひいつか見てみたいです。ワークショップ映画で、冨樫監督と一緒にいろいろな試みをされていたんですね。それを経て臨まれた『天使の卵』はいかがでしたか?
あれは頑張ったと思います(笑)。当時僕は34歳で、あの時代のカメラマンとしては若かったんですよ。あの頃はまだ、全国規模の映画はフィルムで撮るのがほとんどで、カメラマンにも当然フィルム経験が必要だから、今よりもなるのが大変だったんですよね。しかも冨樫さんは相米慎二監督の元で助監督をやっていましたから、スタッフも相米組の流れを汲んだベテランの方が多くて、「この若いあんちゃんが、大丈夫なのか?」という空気の中でやっていました。監督とプロデューサーの一人が僕を推してくれたけれど、別のプロデューサーは反対していたようでしたし。
ですが、撮影開始から一週間後の初回ラッシュで、その空気が変わりました。現像場から上がってきたラッシュを初めてみんなで見て、まず僕自身、思い通りに撮れているなと思いましたし、ほかのスタッフや反対していたプロデューサーにも「よかったよ」と言ってもらえたんです。すごくほっとしたのを今でも覚えています。それ以降はかなりやりやすくなりました。
――この作品で、優れた新人撮影監督に与えられる「三浦賞」を受賞されたんですね。
そうです。ありがたいことに。
この作品で、冨樫さんはかなり自由にやらせてくれました。長回しが基本で、特機部もついていて、クレーンやレールをすぐに準備できる環境にあり、ライティングも大きなライトを使ってやってもらえて……。好きなことができる、贅沢な現場でしたね。
―――その後また冨樫監督と組まれたり、中国映画の撮影をされたり、多様な現場に参加されていますね。最近のお仕事で印象に残っている作品は何ですか?
今井文寛監督の『カゾクデッサン』。自主映画ですが、自分のやりたいことが詰まっている特別な作品です。監督が以前からの友人であったこともあって、のびのび撮影でき、上がりもよかったと思っています。編集も任せてもらい、監督と二人で納得のいくまで作業ができました。そんな現場は滅多にないですから、思い入れはひとしおです。
――『カゾクデッサン』は蓮實重彦さんに絶賛されていましたね。
そう、もう、本当に「やってきてよかった」と心から思いました。映画祭には全く通らなかったので……。
――さっき仰っていた、「見ている人は見ている」という話に繋がりますね。
本当にそう思いました。山根貞男さんと蓮實さんが評価してくださって、自分たちがやってきたことは間違いじゃなかったんだって。
実際この映画は、題材は全然代わり映えしないありふれた家族の話で、社会的な問いもないけれど、描き方でやりたいことができて、題材ではなくて、その描き方を見てくれている人がいた、ということが大きかったです。
――撮影の現場で楽しいこと、大変なことは何ですか?
楽しいのはやはり、現場で何かが生まれた瞬間でしょう。「あ、これ!」という瞬間があると、やめられないですね。
逆に、演出やカット割が予めガチガチに決められていて「この通り撮ってください」と言われてしまうと、なかなか楽しめないのが正直なところです。
ですから、なるべく現場で作っていくタイプの監督と仕事ができたらいいなとは思いますね。
――映画が好きな方で、カメラマンと映画監督どちらを目指すか悩んでいる方も多いと思うのですが、何かアドバイスはありますか?
今時点で監督になりたいという気持ちがある人は、監督になるといいと思います。「撮影が好き、カメラマンになりたい」とはっきり思っているのであれば、撮影でもいいかもしれませんが、撮影はどうしても、組む監督によって変わってきますから。
映画が好きということであれば、やはりまずは映画監督を目指すのがいいと思いますよ。
――「これから映画をやりたい」という方にメッセージをお願いします。
まずはとにかく「映画を見てください」ということですかね。
僕も専門学校時代に先生たちに何度も言われたことですが、「教えることなんてないんだよ。現場に出るしかないんだよ」と言う人がたくさんいるんですね。それはまあ、正しいんです(笑)。でもやはり、学校で教えられることもあるし、それと同じ意味で、映画を見るということの中に無限の学びがあるので、それと現場とのフィードバックをうまくしていくのが、一番効率のいい学び方なのではないかと思います。「現場に出る」というのはスタッフとして入るというのもあるし、今だったら自分で自主映画を撮るのもいいですね。それと、学校なり、映画を見るということとのフィードバック。「なんであの映画みたいなことができないんだろう」とか、「あ、現場ではこう見えるのか」とか、そういうことを自分の中で毎回突き合わせることができれば、一番効率的なんじゃないかと思います。
あともう一つあるのが、自主映画では監督が自分で脚本も書くことが多いと思いますが、できれば誰かほかの人の書いた脚本でも撮った方がいいんじゃないかと思います。自分の脚本だとどうしてもお話を気にしてしまって、演出に目がいかなくなるんですよ。他人の脚本だと、その脚本を生かすにはどう演出すればいいかということが仕事になってくるので、かなり勉強になると思います。日本映画に顕著な傾向だと思うんですが、監督をやっている人が、脚本を認められて監督になったのか、演出が認められて監督になったのか、よくわからないんですよ。ただメジャーで映画を撮るときにはほとんどの場合、脚本家は監督とは別にいるわけです。脚本で認められて世に出た監督がそういった仕事をする場合に、演出する力がないことが露呈してしまうわけですね。そういう意味では、最近はテレビ出身の監督の方が演出がうまいという傾向もあるかもしれません。テレビドラマは基本的に脚本家が別でいますから。なので映画を目指していている人も、意識的にそういった訓練をしてみるとよいと思いますよ。
――具体的なアドバイスをありがとうございます。中澤さんとお話していると、ついマニアックな映画談義になってしまいます(笑)。講義ではさらにディープなお話を聞けますので、ぜひ興味のある方は映画監督コースに入っていただければと思います! 今日はどうもありがとうございました。
●中澤さんが撮影を担当された短編映画『花咲く頃に、僕らは』が、Youtubeにて公開中です。ぜひご覧ください。