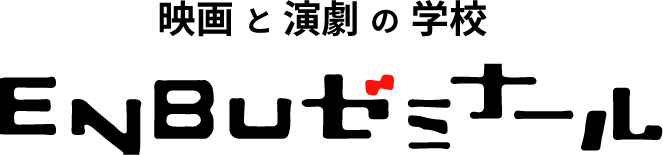GRADUATE
INTERVIEW 03
卒業生インタビュー
佐藤陽子さんインタビュー
映画監督
佐藤 陽子
Yoko Sato
PROFILE映画監督コース 2018年度卒業
2019年4月 ENBUゼミナール監督コース卒業。 女性×働くに興味があり、2013年~2017年まで働くママのロールモデルを紹介する勉強会を主催。より多くの方に情報を届けるために、映像制作という手法に切り替えることを思い立ち、2017 年から映像制作を学び始める。 ENBUゼミナールの卒業制作である中編映画『わたしのヒーロー』(39分)があいち国際女性映画祭2019を始め、多くの映画祭に入選。2021年には障害者の「きょうだい」を描いた中編映画『ふたり〜あなたという光〜』を監督。精力的に制作活動を進めている。興味のあるテーマはジェンダー、夫婦のパートナーシップ、女性×仕事など。
映画のもつ力に気づき、作りたいと思うようになった
――映画作りに興味をもったきっかけは何ですか?
映画を見ること自体はずっと好きでしたが、作る側に回ることは考えたこともありませんでした。その考えが180度変わったきっかけがいくつかありました。
まず、原体験とも呼べるような映画体験がありました。ある時、『マダム・イン・ニューヨーク』という映画を見ました。この映画は、お料理上手だけれど、英語が苦手で、夫にも子どもにも笑われていたインド人の主婦が、姪の結婚式に出るためにNYへ行くのですが、そこでも英語ができなくて悔しい思いをする。そこで一大決心をして英語学校に通い、最後は家族を見返すような素晴らしい英語のスピーチをする、というお話です。作品としてはとても地味ですが、私にとっては、自身の映画観がガラッと変わるほどの衝撃を受けました。この映画の主人公に、私の母の姿を見た気がしたのです。お金を稼いでいないからという理由で、どこか肩身の狭い思いをしていた母。夫婦は対等なのだから、もっと堂々としていていいのにと、子ども心に思ってきたけれども、そんな母の姿を見たことは一度もありませんでした。本人にもその意欲がないし、それは仕方のないことなんだと、モヤモヤした気持ちに蓋をして生きてきました。その固く閉じた蓋をポーンと開けたのが、この映画でした。そこには、自分の尊厳を守るために、自分で立ち上がる主人公の姿があり、私が見たかった母の姿がありました。どこにも置き場がなかった私のモヤモヤをこの映画が解放してくれたような気がしました。「映画にこんなことができるんだ!映画はただのエンタメじゃないぞ」と認識が変わった瞬間でもありました。
それと同時並行で、私は30歳の時から、仕事の傍ら、働くママ向けの団体を立ち上げて、仕事と家庭を両立していくための情報を届ける勉強会を開催していました。一緒にがんばって働き、夢いっぱいだった友人の女性たちが、30歳になり結婚や出産がリアルになった途端、もう夢を語らないどころか「仕事を続けられない」と言うようになったからです。
ですがその活動を4年ほど続けた頃、活動の潮目を感じるようになり、より多くの方に情報を届けるためには勉強会ではなく、もっと手軽なコンテンツにして伝えられないか。考えに考えて、映像制作を思い至りました。特にストーリーがあるドラマが好きだったので、ドラマはどうやって作れるのかと調べていたら、世の中には映画学校があるということを知りました。ただ、「映画を作る側に回る」ということが、よく考えなくても大変そうだったので、しばらく踏ん切りがつかず躊躇しておりましたが、とにかくやってから決めようと思い、映画学校に行ってみることにしました。
――大切なメッセージを人に届ける方法を模索する中で、映画にたどり着いたんですね。まずはニュー・シネマ・ワークショップ(NCW)に半年通われたんですよね。
都内で仕事をしながら通える映画学校を検索したところ、映画美学校とENBUゼミとNCWが出てきました。ENBUゼミナールに興味をもちましたが、映画を学ぼうと決心したタイミングが秋で、入学時期まで半年空いてしまうのがもったいないと思い、まずは半年間のNCWベーシックコースに入学しました。35歳の時です。
NCWでは、10分の短編映画を初めて作りました。初めての作品なので突っ込みどころ満載の仕上がりでしたが、スタッフやキャストなど多くの方の熱意と技を結集して作るプロセスそのものが、とてもクリエイティブで面白いなと感じました。
――映画作りは面白い、もっとやりたいと、その時に思われたんですね。
そうですね、もっと勉強したいなと思い、2018年の春からENBUゼミに入りました。
実は、NCWに入学してショックだったのが、自分自身の「学ぶ力」が若いころと比べて衰えていたことです。NCWは授業が週1回なんですが、週1回だと覚えられないんですね。ENBUゼミはもうちょっと授業数があるので、最初はきつくて通いきれないんじゃないかと思っていたのですが、私の年齢だと怠けてはいけないんだと思いました(苦笑)。また1回でも映像制作を経験したことで、一つ一つのプロセスを、改めてじっくり学びたいと思っていたこともありました。特に脚本や編集は丁寧に学びたかったですし、当時市井昌秀監督が講師をしていた「専任講座」という授業が通年あり、現役の映画監督からじっくり丁寧な指導を受けられると聞いて、しっかり学べそうだなと思いました。映画館で上映の機会があるのも、魅力でした。
入学してよかったのは、熱意のある仲間と出会えたこと

――実際にENBUゼミに入ってみて、どうでしたか?
とてもキャラの濃い生徒たちが集まっていて、刺激を受けました(笑)。これまでの人生で出会ってこなかったような、バラエティーに富んだ背景や価値観の同級生たちは個性的なだけでなく、とても映画好きで、熱意のある仲間と出会えて本当によかったです。周りの温度が高いと、自分の温度もだんだん上がってくるので、それと共に卒業制作まで駆け抜けることができたと思います。
卒業後も映画熱の冷めない人が、同級生にも先輩後輩方にもたくさんいるので、いざ自分が作品を撮ろうというときに声をかけられるのもありがたい。今年短編を撮った時にも、ENBUゼミの繋がりをフル活用して、2012年卒の方から同級生、現役生の方にもスタッフとして入ってもらいました。みんな、しんどい撮影に文句も言わず耐えてくれて、むしろ「いい作品つくりましょう」とポジティブな声がけをしてくれる。映画に対する熱意がないとできないことだと思います。また、映画祭に行くと、様々な代のENBU生にお会いすることがあり、「私もしぶとく頑張ろう」と思えます。ENBUゼミの人たちは、しぶとさがありますね。みんな、表現したい気持ちがすごく強くあるのだと思います。
――確かに、卒業してからも、何らかの形で表現を続けている人が多いですね。
――ENBUゼミの中間制作では、『仮面夫婦』という作品を撮られました。医師として働くお母さんが主人公の作品でしたね。
脚本講座で榎本先生にプロットを見せたとき、「働くママの映画なんて誰が見たいんだ」とバッサリ斬られたことを、今でも覚えています(苦笑)。「ママが大変だなんて、世の中の人はみんな知っているんだから、何の興味も湧かないね」と。それでも「なにくそ」と思って撮りましたけれど、「自分の撮りたいものだけを撮っても仕方ない」ということも学びました。先生のおっしゃる通り、新しくないテーマを扱う時、何か工夫がないと、多くの人が見たいと思うような作品に仕上がりません。ただ、その時には理解できないこともあるけど、全力でトライするということが大事ですからね。全力でぶつかって大きく学ぶことができました。
同級生の作品を見ることもとても楽しく、刺激を受けました。自分からは決して出てこないぶっ飛んだ表現を見ることができて、感動しました。
ただ、楽しかったけれど、中間制作の後、どっと疲れましたね(笑)。
――そんな疲れ切った状態で、休む間もなく卒業制作ですよね。
中間制作は夏に撮影して、11月に上映して、12月頃、「え、次の上映が4月ってことは、2月に撮るのか?」。精神的にも肉体的にも経済的にも全然回復してないのに、また撮るんだと(笑)。
ですが、私の場合、疲れ切っていたからこそ、よかったこともあったのかなと思っています。『仮面夫婦』が完成した後、せっせと上映会を自分で開催していたのですが、見に来てくださったママから「パパも大変だから、今度はパパが主人公の映画を撮ってほしい」と言われ、その時に「あぁ、そうか。撮ってみるか」と素直に思ったのです。そうやって自分の我ばかりでないテーマ設定ができたのは、お疲れだったからかもしれない(笑)。
――そうして、育休を取るパパを主人公にした『わたしのヒーロ―』を撮ることにしたんですね。
そうです。
卒業制作でよかった点が2つあって、まずは、脚本を書く際に取材をしたこと。ママの映画を作るときには、これまでのママを応援する活動の蓄積があったので、一人で脚本を書きあげました。ですが、パパのお話は、よく考えてみたらほとんど聞いたことがなかったので、改めて取材をしたところ、「こんなに大変だったんだ!」という発見がたくさんありました。そんなパパたちの声にならない声が伝わるような作品を撮りたいと思いました。

もう一点よかったのは、外部の映画仲間と出会えたことです。中間制作の時には、NCW時代の同級生に助けてもらったのですが、卒業制作時に都合が合わず、スタッフ集めに苦心しました。ENBUのクラスメイトにも勿論参加してもらいましたが、皆自分の作品づくりに忙しい。そこで人づてに紹介していただいたのが、卒業後も一緒に作品を作っている角さんという撮影監督で、角さんから更に映画仲間をご紹介いただき、皆さん私よりも本格的に映像を勉強されている方々で、現場で本当に色々なことを教えていただきました。
撮影後も「映画祭にも出しますよね?」と促され、「あ、もちろんです(映画祭というものがあるんだ)」と。(笑)
そして、初めて応募した「あいち国際女性映画祭」で、グランプリと観客賞をいただきました。この映画祭は愛知県の男女共同参画の財団が運営を担っている映画祭で、私の映画のテーマとピッタリ合致しており、運命的なものを感じました。
――佐藤さんのためにあるような映画祭ですね。
本当にそうなんです(笑)。受賞後に、作品をめぐる状況も一変しました。以前は、自分から営業をかけても全然反応がなかったのですが、受賞後は企業様や自治体様から「上映したい」とお声がけいただくようになりました。制作した2019年から既に2年経っておりますが、2021年現在でも月1~2回ほど、全国各地で上映していただいております。
これは本当にラッキーだったのですが、偶然取り上げた「男性育休」というテーマが、今とても旬なんです。制作時には全く意識していなかったのですが……。法律が改正され、今後は男性も育休を取るように、企業も努力していかないといけないのです。新しい価値観に適応していかないといけないという時に、映画はソフトな入口としてニーズがあるようです。こうした動きのおかげで、『わたしのヒーロ―』は上映料だけで制作費を回収することができまして、制作スタッフもとても驚いておりました。
――それはすごいですね。今までの活動の積み重ねがあったからこそだと思いますが、これから映画を作る人にとっても勇気が出るお話だと思います。
必要とされる作品をつくる
……ただ、映画祭に応募したり、上映会を開催していると、それだけでも忙しく、卒業後はすぐに映画を撮ろうとは思えませんでした。そして卒業から1年経ち、「撮りたいものを撮り終わってしまい、これからどうしたらいいのだろう?」と岐路に立っている時に、今一緒に組んでいる三間プロデューサーとの出会いがありました。
――最近佐藤さんが監督された、障害者の家族をテーマとした2作品のプロデュースをされている方ですね。
そうです。ある日、『わたしのヒーロ―』を見た三間さんから連絡をいただき、「映画を撮りたいと思っているから、いろいろ教えてほしい」と。話しを聞いてみると、障害をテーマにした映画を制作したいということで、映画学校に通うところから検討していたので、鋭いビジネス感覚と人を巻き込む力を持つ彼女にプロデューサーという関わり方もあると伝えました。
その後コロナにより緊急事態宣言が出された時に、それまでは人生の岐路に立ってモヤモヤしていたのに、今度は「もう映画は撮れないのか」と悶々としている自分がいました。(笑)そして「最後にもう一本撮るとしたら……」と考えていたときに、三間さんの障害者の「きょうだい」として葛藤してきたライフストーリーが思い出され、コロナ明けに私から連絡を取り「三間さんの話を撮らせて欲しい」とお願いしました。そうして撮ったのが、障害者の「きょうだい」を描いた『ふたり〜あなたという光〜』です。
私にとって、自分以外の誰かの大事なテーマをお預かりして撮る経験は初めてだったので、大きな経験でした。また、初めてクラウドファンディングにも挑戦し、三間プロデューサーとチームメンバーのおかげで、583名もの方のご支援をいただくことができ、たくさんの方のご厚意と応援により映画を撮らせていただく貴重な経験もさせていただきました。本作は関わってくださったスタッフキャスト全ての方のおかげで、最終的にいい作品を作ることができたと思います。そして現在は自主上映会方式で、教育機関や障害に関わる団体様を中心に上映のお声をいただいています。
――『ふたり~あなたという光~』の後、今度はヤングケアラーを題材にした短編を撮られました。
『ふたり~あなたという光~』の上映を続けていく中で、新しいご縁をいただきました。障害者の家族支援活動をされている持田さんから、18歳以下の障害者の「きょうだい」が直面する課題もぜひ映像化して欲しいとご依頼があったのです。18歳以下の「きょうだい」は、最近世間でも注目を集めているヤングケアラーに該当するケースが多く、今のタイミングを逃さずに、多くの人に実態を知ってもらえるような短い映像作品を作りたいと。短編を撮るのはNCW以来で、想像以上に苦戦し自信を失うこともありましたが、皆さんの力を借りて、何とかご要望に添えるものは作れたかなと思います。
12月18日から、Youtubeチャンネル「ケアラーTube」にて公開しますので、ぜひご覧いただけたらと思います。『陽菜のせかい』(16分)という作品です。

小さくても、誰かのモヤモヤを解放するような作品を撮りたい
――今後やっていきたいことはありますか?
近いところでは『ふたり』の続編を、諸々のタイミングが揃えば作りたいと思っています。
先のことは、具体的に考えているわけではないですが、今回のように、このテーマの映画が欲しいという依頼主様がいて、ご依頼いただけるのならば、その大事なテーマを映像化していくことは挑戦し続けたいと思っています。これまでの人生で「(こういうシーンを)見たかったけれど、見られなかった」「(こういう言葉を)言ってほしかったけれど、言われなかった」ということは、誰にでもあると思うんです。『マダム・イン・ニューヨーク』が私を解放してくれたように、小さくても、そういったことを届けられる作品を作りたいです。
今後いろんなご縁があったらいいなと思います。
――映画の魅力は、何だと思いますか?
私は働くママ向けの勉強会を開催していましたが、映像は(情報が)何倍もスッと入ってくると言われました。映像や物語の力は大きく、大真面目に難しい話をされるより、「この主人公の○○さんが困っていて……」というお話を見た方が、よほど人の心は動くと感じます。また、映画のフットワークの軽さにも大変な魅力を感じています。データさえあれば、どこでも上映することができ、私がその場に行かなくてもたくさんの方が見てくださる。制作は本当に大変ですが、やる価値あるなと思います。
――これから映画をやりたいと思っている人たちへメッセージをお願いします。
そんな偉そうなこと……(笑)。
私が言えるとしたら、映画制作は何歳で始めたとしても、その時にしか作れない作品があると思います。それはとても貴重なものなので、人と自分を比べずにぜひトライして欲しいです。
――ありがとうございます。これからもご活躍を楽しみにしています。