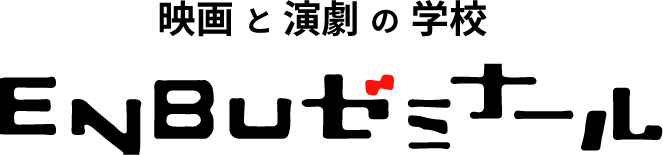GRADUATE
INTERVIEW 04
卒業生インタビュー
市井昌秀さんインタビュー
映画監督
市井 昌秀
Masahide Ichii
PROFILE映画監督コース 2003年度卒業
1976年4月1日生、富山県出身。俳優・柄本明が主宰の劇団東京乾電池を経て、ENBUゼミナールに入学し、映画製作を学ぶ。04年に、ENBUゼミナールを卒業後、初の長編作品となる自主映画「隼(はやぶさ)」が06年の第28回ぴあフィルムフェスティバルにおいて、準グランプリと技術賞を受賞。長編2作目となる「無防備」が第30回ぴあフィルムフェスティバルにおいてグランプリと技術賞、Gyao賞を受賞する。そして同年開催の第13回釜山国際映画祭のコンペティション部門にてグランプリ受賞、翌年の第59回ベルリン国際映画祭フォーラム部門にも正式出品され、国内外から高い支持を得た。13年には、初の商業映画「箱入り息子の恋」が公開。同年のモントリオール世界映画祭「ワールドシネマ部門」に正式出品。14年、日本映画監督協会新人賞受賞。15年、初のTVドラマとなる「十月十日の進化論」(WOWOW)を監督。同年、ギャラクシー賞のテレビ部門において奨励賞、日本放送民間連盟賞及び東京ドラマアウォード2015において優秀賞受賞。「僕らのごはんは明日で待ってる」(17)、「ハルチカ」(17)。「台風家族」(19)。最新作は「犬も食わねどチャーリーは笑う」(22)。
初めて映画を作ったとき、すべてを捧げられると思った
――映画を作るようになったきっかけを教えてください。
最初に興味をもったのはお笑いで、大学在学中から卒業後の数年間、ユニットを組んでお笑いライブなどの活動をしていました。その後脱退し、ピンで活動しているうちに演技に興味が出てきて、劇団東京乾電池の俳優養成所へ1年間通いました。お芝居を学ぶのはとても楽しかったのですが、養成期間が終わった段階で劇団員に選抜されず、その後は2年ほど普通に働きながらたくさん映画を見たり、本を読んだり……。そして3カ月ほど一人でアジアを旅して、帰国後にENBUゼミの映画監督コースに入りました。
入学したのは、脚本を勉強したいと思ったからです。乾電池の養成所時代にいろいろな戯曲に触れる中で、シナリオを自分で書き、演じてみたいと思うようになりました。また旅の過程で現地の人々と触れ合い、どんな場所でもそこに生きる人間こそが魅力的なのだと感じ、きちんと「人間」を描く物語を作りたいと思いました。映像に特化し、学費も安く、当時は秋入学もあったので、ENBUゼミに入学しました。
――ゼミでの生活はいかがでしたか?
すごく楽しかったですよ。ENBUゼミを選んでよかったなと思うのは、「映画という高尚なものを作るんだ」というような、敷居の高い感じが全くなかったことです。自分には合っていたと思います。
当時の専任講師の熊切和嘉監督からは、映画と向き合う姿勢のようなものを学びました。また、今もENBUで教えてらっしゃる榎本さんの脚本講座も、すごく勉強になりました。
入学から半年後の中間制作で、初めて映画制作をし、脚本・監督を担当しました。それまでは脚本を書くこと、演じることが興味の中心だったのですが、経験してみて「監督って楽しいな」と思いましたね。どうしたらお芝居がもっとよくなっていくか、どう撮ったら面白くなるか、ということを考えるのに夢中になって、中間制作が終わったらすぐに、卒業制作のシナリオを書き始めました。卒業制作の撮影も、とても楽しかった。「この先ズタボロになったとしても、映画を作るということに対しては、自分のすべてを捧げられる」と、その時に思いました。
――ENBUゼミでは卒業時に作品を上映する機会もありますが、いかがでしたか?
中間制作、卒業制作と2本、劇場で上映してもらって、当時なりに評判は悪くなかったです。ただ、作品をPFF(ぴあフィルムフェスティバル)やゆうばり(国際ファンタスティック映画祭)に出しても通らなかったので、まだまだ壁があるのかなと思いました。
僕は映画を作り始めた最初の頃から、観客を楽しませるエンタメ性を意識していました。芸人気質のようなものかもしれません。見る人にとってあまりにわかりにくいことは、やりたくないと思っていたんです。映画祭に落ちたことを契機に、改めてそのことを見つめ、作品を届ける方向を、より一層考えるようになりました。一方で、自分の作家性……と言うと大げさですが、自分自身の癖や好みのようなものは、消し去りたくない。ある意味永遠の命題のようなものですが、それらをどう両立していくかという課題に、拙いながら挑戦し始めたのが『隼』(2005)でした。映画祭に落ちた半年後に撮った作品です。
――『隼』は見事、PFFで準グランプリと技術賞を受賞されました。古い一軒家に住む貧乏夫婦のお話ですね。どうしようもないような人たちを滑稽に、しかしあたたかく描くのは、この当時も現在も共通する市井さんのスタイルだなと感じます。
僕自身、映画を作るようになってからは、やめたいと思ったことは一度もないのですが、映画を見つけるまでは「これでいいのか」と悩んだり、何かを始めてもやめてしまったり、よくわからなくなってふさぎ込んでいた時間がありました。そういう時間も肯定したい。それに、他の人たちも同じようなことで悩んでいるから、そういう自分のダメな部分も見せていくことで響くものがあると思います。自分に近いものを描くことで、自然と嘘が減っていきますし。
――さらに1年後には『無防備』を撮られています。ご自身の奥様のリアルな出産を撮ったシーンが、大変印象的な作品ですね。
映画には記録という側面もあるので、妻が妊娠したときに、産まれてくる瞬間を撮りたいと思いました。そういう意味では、『無防備』は初めて逆算的な作り方をした作品でしたね。
オリジナル脚本にこだわる理由
――『隼』は2006年のPFFの準グランプリ、『無防備』は2007年のグランプリに輝きました。ご自身に達成感や変化などはありましたか?
映画祭に入選すると上映の機会があり、作品に対する観客の反応をその場で見られることが嬉しかったです。『無防備』は映画祭のプログラムだけではなく劇場公開もして、いろいろな方に見ていただき、自信にもなりました。
ただ、「一般の人にも届くものを」という、大きな目標に到達した感覚はまだなかったですね。
PFFには「PFFスカラシップ」という制度があって、受賞者がそれぞれ次回作の企画を提出し、審査の結果選ばれると、製作の機会が与えられます。僕は2回チャンスがありましたが、2回とも落ちてしまいました。そういう意味でも、まだまだ課題が多いと感じましたし、「これからどうしていこうかな」という気持ちもありました。映画を撮っていくんだという思いは絶対に消えないけれど、立て続けに自主映画を作ったことで借金が溜まっていたので、自主制作はもう当分できないだろうと……。子どもも生まれたので、『無防備』の後しばらくは、派遣社員として働きながら、コツコツとシナリオを書き続ける日々でした。書いたものをプロデューサーに見せたりもしていましたが、映画化には結び付きませんでしたね。
――厳しい現実ですね……。ただ、そんな時期を経て2012年には『あの女はやめとけ』、2013年には『箱入り息子の恋』と、監督作が続きますね。どういったきっかけがあったのでしょうか?
『無防備』を見てくれていたキノフィルムズのプロデューサーから、数年越しに連絡があり、「代理お見合いについての映画を作りませんか?」と誘いを受けました。時代性があって共感もできる面白いテーマだと思い、脚本を書いていったのが『箱入り息子の恋』です。
そちらの企画が進んできたころに、ENBUゼミの代表の市橋さんからも声がかかって、シネマプロジェクトというものを始めるから、監督をやってみないかと。それが『あの女はやめとけ』ですね。どちらも2012年に撮影しました。それまでなかなか映画が撮れなかったのに、たまたまタイミングが重なったのは不思議だなと思います。
――『箱入り息子の恋』は初めての商業映画となりましたが、自主映画との違いは感じられましたか?
商業映画では仕上げの作業をスタジオに入って行うので、その過程は、最後まで自分で作業をしていた自主映画と大きく違うところです。ただ、撮影現場で監督がやるべきことは変わりません。関わってくる人が多くなる分、プレッシャーはありますけどね。
――その後はコンスタントに映画やドラマのお仕事をされていますね。
そうですね。でも実際に完成し公開されたもの以外に、お話をいただいたけれどお断りしたものや、受けたけれど実現に至らなかったものもありました。お蔵入りになったシナリオが7~8本はありましたね。
そういった経験を経て、なるべくオリジナル脚本で進めていこう、という方針が自分の中にできました。現実的にその方が、書いたものが映画になる可能性が高い。映画の企画が何らかの事情で頓挫した場合、原作のあるものだと、それを元に書いた脚本もお蔵入りになってしまいますが、自分のオリジナルであれば、また別の機会をめざすことができます。ただし「もう絶対に原作ものはやらない」ということではなく、共感できる内容で、製作が確実に実現するのであれば、ぜひやりたいと思っていますが。
――いずれの場合も、脚本は必ずご自身で書かれるという姿勢は変わらないですか?
そうですね。まだまだ拙くても、自分の武器は脚本だと思っています。僕は自分が書いた脚本があって初めて、監督としても成立していると思うんですね。そういう意味では「映画監督です」とシンプルに言い切れないようなところもあります。例えばいろんな映画監督の元で演出論を学んできていて、「どんな脚本でも面白い映画にするぞ」という人は、監督として技術をもって仕事をしているという自負がもてると思うのですが、僕はずっと「自分の好きなようにやればいい」と思って実際そうやってきただけで、だからこそ自分の作家性というものにこだわっています。
やりたいようにやることが大切

――脚本のアイディアはどこから湧いてくるのですか?
場合によりますね。普段からちょっとしたことでも、何かひっかかったときにはメモをとっていて、後でそれを読み返して広げていくこともあります。何も思い浮かばずにひたすら歩いたり、じっと机に向かって絞り出していくようなときもあります。僕にとっては、映画作りの中で一番楽しいのも、一番苦しいのも、脚本を書くことです。ある程度見えてくれば楽しいのですが、それまでは苦しい。
――映画監督コースに入ってくる生徒さんから、映画を撮りたいけれど何を撮ればいいのかわからない、撮りたいものがない、と言う声を聞くことがあります。
無理に「何を撮りたい」と決めるのではなく、自然に出てくるもの、テーマのようなものが出てきてから書いてみるといいのではないでしょうか。気負わずに面白いと思うものを書いていって、テーマが後から見えてくることもあります。「テーマ性」と言うと重たい感じがしますが、普段ニュースを見たり生活する中で感情が動く瞬間、小さくても怒りや違和感を覚えることがあれば、そこから生まれてくるのではないでしょうか。
少なくとも、アウトプットができないのであれば、インプットしていったら何かが出てくると思います。インプットというのは映画に限らず、現実の情報や生活、人とのやりとりや関係性など……その中で立ち止まって、虫眼鏡で見るようにじっと見つめて考えてみる。単純に「かっこいい映画を撮りたい」という風に漠然としている段階だと、何を撮っていいかわからないものですが、ひとつテーマが見えれば、勝手に膨らんでくると思いますよ。
――市井監督には2015年~2020年の6年間、ENBUゼミナール映画監督コースの専任講師もご担当いただきました。いろいろな生徒がいたと思いますが、いかがでしたか?
たくさん刺激を受けました。僕は自分のことを、映画監督として先輩だ、という風には全く考えていなくて、常にライバルだと思ってみんなと接してきました。だから、毎年新鮮な気持ちをもって入学してくる生徒たちに対して、彼らの初期衝動が羨ましいとか、「あの頃に戻りたい」とは全く思わなかったですね。僕自身が未だに初期衝動をもって映画を作っているので。ライバルとしてみんなの作品を見る中で、「新しい感覚に触れた」という刺激を受けることがありました。
――映画を作ってきてよかったと思うこと、これから挑戦したいことがあれば教えてください。
僕が書いたセリフを俳優が言ってくれて、それに対しどう面白くしていくかというのを、たくさんのスタッフが集まり考えていく。自分のシナリオを設計図として、大勢の人が力を合わせて作品を作っていくこと自体が僕にとっては本当に嬉しくて、喜びなんです。近視眼的かもしれないけど、この喜びがあるから映画を撮っていてよかったと思うし、これからも続けていこうと思います。
2020年に新型コロナウイルスが流行したときにも、正直、将来を考えて不安になるようなことはなくて、「この経験もいつか映画になっていくんだろうな」と漠然と思ったぐらいでした。緊急事態宣言下で外出ができないので、家で脚本を書き続けていたら、知り合いのプロデューサーに「こんな時によくできるな」と言われましたが……(笑)。パンデミックで世界が変わっても、物語や映画というものは、絶対になくなることはないと思っていたんです。もしなくなったら、僕は生きる気力がなくなるし、他のたくさんの人々もそうだろうと思います。ただ、単館映画館が危機に陥っている状況には胸が痛んで、映画館が減ってしまったらとても寂しいとは思いました。一方で配信が増えていくという時代の流れを、柔軟に受け容れていきたい気持ちもあります。どういった形になっても、僕自身はこれまでにやってきたこと、脚本を書いて映画を撮るということを続けていきます。
――映画をすごく信じてらっしゃるんですね。
――最後に、これから映画を作っていこうという人たちへメッセージをお願いします。
ENBUゼミの講師をしていたのに、矛盾した言い方かもしれませんが……まずは誰の言うことも聞かずに、好きなように1回撮ってみたらいいと思います。思うままにまず1回撮って、誰かに見せて、その後どうするかはその人次第。僕はいつもそうやってきました。人の意見はとても大切で、いいアイディアなら柔軟に取り入れることで作品がよりよくなりますし、取り入れなかったとしても、揺さぶりが入ることで「自分はこうしたいんだ」ということがわかる。「自分はこうしたい」ということの強度を上げるためにも、人に見せることは必要です。その繰り返しでしかない。今はクリエイターにとってはとても恵まれた時代で、作品を見てもらいたければYoutubeに上げることもできるし、それですごく面白ければ必ず火がつくわけじゃないですか。作って発表する、ということに関して、やらない言い訳ができない時代ですよね。恐がらずに行動していくことが大切だと思います。
――ありがとうございます。今後も市井監督の作品を楽しみにしています。
★市井昌秀監督の最新作『犬も食わねどチャーリーは笑う』は、2022年9月に公開!ぜひ劇場でご覧ください。
映画『犬も食わねどチャーリーは笑う』公式サイト:https://inu-charlie.jp/